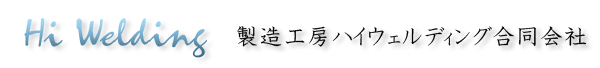欠けたハンマー
わたしは独立するまでに溶接工として、合計四つの会社を渡り歩いてきたのだが(うち、二社は今はない)、これといった自分の道具箱を持ち歩いてはこなかった。
個人専用で使っていた道具類はすべて会社が購入した会社のの持ち物であり、いくら愛着があろうとも退社時に返却しなければならなかった。
熟練の渡り職人のように自前で少しづつ道具をそろえようかとも思ったが、他に自分の知らない良い道具があるんじゃないのかと思ったり、道具にこだわらずにど んなものでも使いこなしてみせる、といったような気負いがあったように思う。溶接機にもこだわらなかった(というか、もちろんこだわれなかった)。すでに そこにある溶接機を試してクセをつかみ、自分がなじめるように徐々に調整していく。その過程がまた楽しくもあった。
溶接工が一番使う道具といえばハンマーではないだろうか。仮付け後の修整、歪み取り、溶接部の延し等、常に手の届く場所にないと作業が進まない程、重要な道具のひとつである。
それまでいくつか使ってきた借り物のハンマーは、会社からの借り物だけあって(意識の問題かも知れないが)あまりしっくりしないまま、こういうものなんだろ うなと使っていた。馴れないハンマーだと頭の角を当ててしまい、製品に打痕をつけてしまったこともしばしばだった。それが恐いと思いきり叩けず、へなちょ こな結果になってしまう。ハンマーを力一杯振り抜けない溶接工は一人前ではない。そういう空気がどの現場でもあり、へなちょこは笑われる対象であった。
四社目に入社してしばらくしてからだった。それまで師匠のEさんのハンマーを借りていた(その会社ではハンマーが余分になかった)。頭の形といい、程よい重 さといい、木の柄の握りといい、年期が入っていて、今までで最も使いやすいハンマーだった。Eさんの道具を借り続けるのは気が引けた。ハンマーくらいは自分で持つべきだ。わたしはこのハンマーと同じ物が欲しいと思い、Eさんにお願いした。
「これと同じハンマーを工具屋に注文してくれませんか、もちろん金は自分で払います」
「今どうかな、同じ物なんてねえんじゃねえか。これはな、俺が小僧っこん時から使っているやつだからなあ、四十年近いやなあ(笑)」
その話は二重の意味でショックだった。同じ物は手に入らないであろうこと。四十年もハンマーが壊れずに使い続けられるのだということ。
「あっ、どっかにあるかも知れねえぞ。ちょっと来てみな」
わたしは別棟の古びた板金工場の奥の薄暗い所へ連れていかれた。雨が降ると床が浸水するその板金工場はカビと埃と錆が混じった、なんとも健康上最悪の臭いがした。
いくつもの腐った木の箱に赤茶色に錆びたヤスリやスパナが放り込まれてある。Eさんが箱をひっくり返して、わたしが中をあさる。その中に両頭が欠け、木の柄の腐ったハンマーがあり、これは使えないだろうと横にはじくと、Eさんが「あった、あった、これだよう」と、お前どこみてたんだよという調子でわたしにせまるように言う。
「だって、これ頭が欠けてますよ、使えないじゃないですか」
「お前、溶接工だろ、盛りゃあいいじゃねえか」
「盛るったって、そんな溶接棒あるんですか?」
Eさんはわたしの言葉を鼻で笑い「タップで盛るんだよ」と、とっておきの秘策を教えてくれた。「硬くていいんだぜえ」
ボー ル盤の並ぶ部屋には切れなくなったタップが箱の中に溜まっていた。。M4位がちょうどいいぞ、とEさんに言われるままM4のタップを10本程掴んで、溶接場に戻った。サンダ−で頭の欠けた周りをなるべく凹凸が少なくなるようにように削り取る。紙ヤスリで錆を落とす。汚れを完全に取り、タップは短いので尻を プライヤーで挟み、さあ溶接だ。普通に盛りゃあいいんだよ。
欠けたハンマーはM4のタップで本当に普通に肉を盛ることが出来た。硬い材料はとかく熱を入れると割れやすいので心配だったが、結果、割れは生じなかった。その後、サンダーでおおまかに形を整え、ベルトサンダ−で仕上げた。以前、 まっ二つに裂けてダメになり、とってあった木ハンマーの木の柄の先を、仕上げたハンマーの穴にしっくり入るようにコンターで角度切りして合わせた。楔には 錆びて使ってないヤスリの先をサンダーで切り落とし、和釘のように仕上げて打ち込んだ。
目からウロコが落ちて、初めて自分のハンマーを手にした嬉しさは忘れられない。この方法を教えてくれたEさんに感謝した。Eさんのハンマーをもう一度見せてもらった。それまで全く気が付かなかったが、よく見るとやはり溶接で盛った跡があった。
「その柄だって何本目か知れねえ、ハンマーなんてもんは欠けるもんなのよう、欠けたら盛りゃあいいだろう、俺ら溶接工なんだからよう」
以後、そのハンマーはわたしにとってなくてはならない道具のひとつになった。