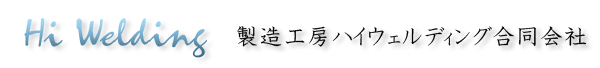自然な建築
これは常々思ってきたことだが、ものづくりの現場において、実際に身体を使ってものをつくる職人と基の設計者が直接対話できることほど幸福な関係はない。
中途半端な組織を持った企業ほど、その間に何人かの伝達係とでも呼びたくなる管理者を配置させたがる。まるで「悪夢の伝言ゲーム」をしているような気分になることもしばしばだ。
わたしの知る限りでいうと、若くて(年齢ではなく気持ちが)情熱があり、今までにない新しいことをやろうとする気概のある設計者ほど、前線にいる現場の職人のもとに足を運び、ものを聞きたがる。しかも謙虚に。職人の気質をよくわかっているのだと思う。たいがい職人はぶっきらぼうで、口が悪く、頑固で、そう簡単にとっておきの情報を教えたりしないものなのだ。
うまい設計者は少しだけバカなふりをする。「それはすごいっすね。思いもよらなかったなあ。目から鱗ですよ」そうはいっても専門的な話なので、レベルの高い 内容だ。普段は口下手な職人も、そういうおだてには弱い。「なんだい、何年設計やってんだよう」などと、冗談まじりに笑いながらその関係性が生まれたらしめたものだ。設計者は少しづつ、本質に向かうように誘導しながら迫っていく。まだ誰も実現させたことのない困難な新しい技術の核心に。設計者は腹の中に組 み合わせのアイデアを抱えている。
「で、何に使うんだい?」日々、職人はものをつくってはいるが、それが実際にどういう使われ方をするのか を本質的に知ることはまれだ。そこで設計者はそのディテールを正直に包み隠さず告白する。「実は・・・」と。そこまでいったら、もうバカなふりを捨て、充分な下調べも含めた自分の知っている全知識を動員して職人に本気でぶつかっていくのだ。正確に職人に伝わる言葉だけを丁寧に選びながら。もしもこの時に嘘や隠し事が含まれていて「おれをダシに何か都合の良い儲け事をたくらんでいやがるな」などと職人が感じたらそれまでだ。職人は人の正直さと情熱には打たれやすい。「おめえさんもおれと同類じゃねえか」と職人が一旦認めた後は話が早い。
かつて経験のない課題が職人に出されたとしても、それは過 去の経験の組み合わせを基にした閃きで、職人は適すだろう解をいくつか呼び寄せることができる。そこから先は言葉にするのが難しい感覚的な、身体的作業が 始まる。設計者もつかず離れず、時には突然さらに困難な注文をずうずうしく言ってみたりする。
「こんなこと思いついちゃったんだけど、いや、まさか、こんなことは無理だよね」
「誰だと思ってるんだよ。このおれをよう」
そうやってタネも仕掛けもあるのだが、傍から見ればマジックとも思えるような技を組み合わせて最適の解を得、設計者と職人の幸福な関係が革新的なアイデアを実現させてしまうのだ。
先日読了した新書「自然な建築」(隈研吾)には、この手のエピソードが満載だ。日本を代表する建築家である隈氏が依頼主の求めに応じるための設計思想を実際 に具現化していくまでの過程が、スリリングに、時には愉快に描かれている。疾走感があるのは隈氏が根本的に若く(気持ちが)、情熱的で、明るいからだろ う。「大人」のチョイスを簡単にしないところが青年らしい。
人間にとっての豊かさを探りたければ、建築をどう生産 するかに対して、われわれは再び着目しなければならない。その大地を、その場所を材料として、その場所に適した方法に基づいて建築は生産されなければなら ない。生産は、場所と表層とを縦に貫く。あたりまえの話だが、場所とは単なる自然景観ではない。場所とは様々な素材であり、素材を中心にして展開される生 活そのものである。生産という行為を通じて、素材と生活と表層とが、一つに串刺しにされるのである。生産とは、そのような垂直性を有する。その結果とし て、自然な建築が生まれる。場所に根をはった、自然な建築ができあがる。
隈氏は20世紀をコンクリートの時代だったととらえている。型枠の作り方を変えるだけでどんな造型をも可能にするという自由で「易しい建築」なのだという。豪華に見せたい場合はコンクリート の上にスライスした薄い石を、ハイテク、未来志向には銀色でシャープなアルミ板を、自然派、エコロジー派を気取りたい時には木の板を貼付けたり、珪藻土を 薄塗りするという「お化粧」次第でローコストなものから高級建築までをカバーできるからだと。
中身が見えないことに、コンクリートの本質があったのである。それゆえ、その上に化粧の上塗りが平然と行われる。そもそも中身が見えていないのだから、その上に何かを重ねて、さらに不透明にしたとしても、その不透明な本質に変化はない。感覚はマヒし、上塗りは日常化する。
隈氏は自然との対比によるモニュメントとしての建築ではなく、自然とのグラデーションによる非モニュメントとしての建築を指向する。中身が見えるように風穴 をあけ、地産の素材を組み合わせることを何よりも優先する。近代のコンクリートによる高層建築が天に向かう垂直性の「串刺し」だとすれば、隈氏の指向する 「自然な建築」とは地の根に向かう垂直性の「串刺し」だといえるだろう。だからラジカルなのだ。
ラジカルと根っこという言葉が同じ語源をもつことを忘れてはならない(フランク・ロイド・ライト)
現場である土地を訪れ、はじめてその土地の素材に出会う。素材は場所によって様々だ。本書では石、杉、竹、日干し煉瓦、和紙などを素材に取り入れた例が紹介 されていて、それぞれの専門家である職人と隈氏が向かい合いながら進行形でディテールが決められていく。たとえばそのなかで生まれた「燃えない杉」など、 ほとんど発明といっていいことをやってのけてしまう。
隈氏と職人との関係性は理想的だ。おそらく隈氏の青年的魅力、そしてその精度の高い言葉と行動力に嘘がないから職人の信頼を獲得できるのだろう。職人は全技術をつぎ込んで隈氏をサポートする。職人だけではない。専門の研究者、大元である発注者、建築という作業にかかわる全ての人を巻き込んでいってしまう力量が隈氏にはある。
おそらく「自然な建築」というのは、大きな寛容の上にはじめて成立する建築なのである。
もちろん、はじめから「大きな寛容」があるのではない。「大きな寛容」は謙虚さからはじまった「幸福な関係」の持続によって、いつしかそこに生み出されているのだ。未来を創造していくためのヒントの一つは、きっとそういうところにあるはずだと思う。