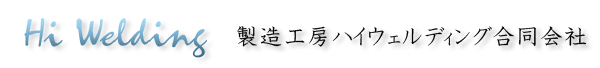追悼 清水邦夫 1
去る4月、近、現代演劇を代表する劇作家、清水邦夫さんの訃報に接した時、わたしはなんとも言いようのない混乱さ、おぼろげな記憶、それとも夢で観た記憶、いや、実はでっちあげの自分にとって都合の良い捏造した記憶、他にもわけのわからない感情やら脳内映像などが無差別に混じり合い、その乱れた状態にしばし陥ってしまった。まるで清水さんの戯曲のなかに出てくる精神が錯乱している登場人物のように。それで、少し整理しなければならないと思った。
「今、思い返すと、誰かほかの人間のような気がする」昔に読んだロバート・B・パーカーの小説「愛と名誉のために」はそんな書き出しで始まっていたように思う。そうやって過去の自分と距離を取り、ポジションをずらすことで、いくばくかは冷静に客観的な事実を記せるのではないかと思い、それに倣ってみることにする。
遠い昔の話だ。1980年代前半、今からおよそ40年近く前、彼は清水さんが主宰していた演劇企画集団「木冬社」の第二期研究生20人程のうちの一人だった。「木冬社」はいわゆる劇団組織とは異なり、清水さんの主に書下ろしの戯曲を上演するために集う文字通りの「企画集団」で、連名制という形をとっていた。これは清水さんの過去の経験から得られた結果なのだと思う。固定メンバーはいるが、束縛が劇団組織ほど強固ではなく、流動的でもあり、しなやかさを保つために独自に考案されたものなのだと思う。したがって「組織、集団」というと何かと起こってしまう「解散」という概念からも開放された、それまでになかった比較的「自由な演劇集団」を目指す意味があったのではないかと思う。
研究生は4月から一年間の研修期間があり、講義、エチュード、ボイストレーニング、ダンスなどの訓練を経て翌年2、3月に行われる卒業公演に臨み、その成果、結果を審査され、その後、正式に連名メンバーに加えてもらえるかどうかが決定される。彼は演出志望であったのだが、木冬社の研究生にそのような枠はなく、何は何であれ、清水さんのもとで生で戯曲を体現し、演劇の現場を学びたかったのだった。
彼はもともと映画監督を志していた。高校生の頃から割と本を読む方だったが、どちらかというと「言葉による文化」をバカにしていた。言葉は日常で使っている。この程度のことなど、やる気になれば、自分でも書ける。それよりも、言葉にできない音楽や美術、映像表現のほうが崇高だ。それらには、言葉を介せずともダイレクトに心情に響いてくる何かがある。言葉は時に邪魔にすら感じる場合がある。そういう意味で映画はそれら総合芸術の頂点じゃないか、そう思っていた。それで彼は今村昌平監督が設立した横浜放送映画専門学院に進学するため、18歳で郷里と決別するように上京したのであった。しかし、ここで彼は決定的に躓く。いざ、自分で映画の土台となる脚本を書こうと試みたところ一向に言葉を紡ぐことができないことに唖然とし、己の無能さ、阿呆ぶりに愕然としたのだった。それまで音楽、映画、美術などから影響を受けた文化的センスは誰よりもあると自負していたのだが、それがただの思い込みによる錯覚でしかなかったことを思い知らされたのだった。ただ、心のなかには常にグラグラと、その形にならない、できない毒素のようなものを抱えていて、それが不意に表に現れて周囲に危害を加えたりすることがないよう、自分で抑え込む必要があることも自覚していた。
「今、自分に必要なものは何だ」と彼は考えた。さして深く考えるまでもなく、それは「言葉」だと結論が出た。まったくもって間違えていたのだった。言葉こそが土台だったのだと気がついたのだった。。頭の先から手足の爪先まで全身に渡って「お前には圧倒的に言葉に置き換える能力が足りないのだ」と身体が叫ぶように訴えているのを耳にした気がして、彼はその場に打ちのめされたのだった。ただ、ここで初めて理解できたことがある。「言葉にできないことを表現するために必要な言葉も存在する」のだと。
それからというもの、彼はよりいっそう書物を読み漁った。小説、古典文学、シナリオ、戯曲。言葉、土台、表現、それらの感覚を意識しながら。難解な言葉が羅列された書物も、言葉の意味やその感覚がわからなくてもとにかく目を通すようにして、未知の言葉でも触れ続けることを優先した。なかでも彼にとって興味を惹かれたのが戯曲の数々だった。なぜか、本来目指しているシナリオよりも戯曲のほうが数段面白く感じられた。舞台を前提にしていることで空間がある程度限られているせいなのか、台詞によって登場人物達が立ち昇ってくる生々しさが他の書物とは異質だった。寺山修司、安部公房、別役実、唐十郎、つかこうへい、野田秀樹・・・そして清水邦夫。その作者の戯曲に出会った時、彼は心のなかでこう叫んだ。「見つけたぞ 何を 清水邦夫を!」
彼はその年の12月の紀伊國屋ホールでの定期公演「とりあえず、ボレロ」の劇団員の役で初舞台を踏んでいた。まだ、研究生の身だったが、出演人数が足りなかったのだった。看板女優である松本典子さんにはなぜか気に入られた。声量があって声が人一倍大きかったのと、高校時代にバンドを組んでギターを弾いていたことや、音楽に詳しかったことで面白がられたのだろうと思った。ある時、アトリエの稽古場で持ち込みでの飲食パーティーがあった時、アコースティックギターがあり、松本さんから「イワシタ、歌え!」と絡まれるような指名があり、浜田省吾の「路地裏の少年」を歌った。「まあ、まあね」松本さんには少し期待はずれだったようだった。
そして、翌年の卒業公演の演目は「楽屋」と「花飾りも帯もない氷山よ」で、彼には二人芝居「花飾りも帯もない氷山よ」の「あいつ」役があてがわれた。演出は清水さんの演出助手であるSさん、相手の「男」役には一期生で、すでに木冬社のメンバーであり「とりあえず、ボレロ」でも独特の役作りで「スキー帽の男」を演じ、注目されていた実力派男優Hさん。「アンリ・ミショーの詩集(小島俊明訳)のことばを並びかえたり、詩集から妄想したものをつらね、構成した(清水さん記)」という難解な戯曲で、稽古はSさんによるダメ出し、ダメ出し、ダメ出しの連続で彼は人格崩壊寸前まで追い詰められたが、それでもなんとかその組んだチームのおかげで、最後の最後にほんの小さな花を咲かすことができ、その結果、連名メンバーに加わることが叶ったのだった。「初演(1976年10月、渋谷ジャンジャンにて、松本典子、吉岡裕一)よりも良かったよ」なんと、そう短く評してくれた清水さんの言葉に彼らは驚喜し、三人で乾杯した。
同じ年、清水さんは大きなプロジェクトを抱えていた。4月、渋谷、パルコ劇場にて行われる「タンゴ、冬の終わりに」の上演だ。その二年前に日生劇場で上演された「雨の夏、三十人のジュリエットが還ってきた」でおよそ8、9年ぶりの蜷川幸雄さんとの作、演出コンビは復活していたが、その結びつきをさらに前進させるべく、超一級品として企画されたものだった。舞台となる映画館、幻の観客たち、タンゴを踊る群衆、コロス的な役割を担う大勢の出演者が必要で、蜷川さん側からはニナガワ・スタジオの面々が、清水さん側からは木冬社の面々が全面的に動員されることになった。
彼にとって、蜷川さん、それと主役である平幹二朗さんとの出会いもまた強烈で衝撃的なものだった。稽古日初日、稽古場であるベニサンピットへ初めて行った時のことだ。すでに舞台となる映画館の客席、階段の美術セットはほぼ形を整えて出来上がっており、出演者、スタッフの簡単な顔合わせが終わった途端、いきなり立ち稽古が始まったのだった。普通は本読みといって椅子に座り、台本を手に台詞を読み上げ、徐々に慣らしていくものだと思っていたのだが、平さんはもう台詞をほぼ頭に入れてきており(もちろん付き人兼プロンプターである、やまび研さんが脇に控えてはいたものの)、舞台の凹凸や雰囲気と交わるべく役に入りきって動き回り始めたのだった。その声、表情、所作を含め、もはや表現などという言葉を超えた人物を目の当たりにして、彼は、この人は今、どこか別の次元から突如この場所に現れた妖怪とか、もののけとか、宇宙人とか、かつて見たことがない存在を目にしている気がしたのだった。
蜷川さんは噂通りのエネルギーの塊のような人で、その初日、彼を含む駆り出されて集まった若手達を前にまず、こう言い放った。まるでアーク放電で伝えるかのように。
「いいか、今のこの時代、才能のある若いやつは音楽に行っている。時代の空気を敏感に感じ取れるのは才能のあるやつだけだ。お前らにはまったく才能がない。そこからがスタートだ」
この後、稽古、本番とおよそ2ヶ月間の間、行動をともにして蜷川さんの気配りや繊細さ、そして少年のような純真さを併せ持っていることに気がついてから振り返ると、この言葉は次のように解釈ができた。
「お前らには才能がない、お前らはバカだ、こんな時代に芝居だなんて。ただ、言っておく。俺はそんなお前らのことがとても愛おしい。手を抜くな。良い舞台にしよう」
舞台は北陸地方のさびれた映画館内。その年に1月に発売されたばかりの戸川純さんのアルバム「玉姫様」に入っている「諦念プシガンガ」のイントロ、打楽器の特徴的なリズムが大音量で流れる中で幕が開くオープニングは、かつて賑やかで観客がいっぱいだった1970年頃の館内の情景だ。幻の観客たちで席が埋まっている。上映されている映画はピーター・フォンダ、デニス・ホッパー、ジャック・ニコルソンが組んだ「イージーライダー」だ。観客たちはその結末を知らずに嬌声を上げて熱狂している。それが一発のショットガンの銃声で静まりかえる。バイクのエンジン音、ピーター・フォンダがトラックを追いかける。トラックがUターンしてくる。二発目の銃声、バイクが吹き飛び、炎上する。
「スローモーション、指先まで全神経を使え!いいか、絶望から始まるんだよ!」
これも戸川純さんのアルバム「玉姫様」に入っていてパッヘルベルのカノンに詩をつけた「蛹化の女(むしのおんな)」が流れる中、観客たちがスローモーションで幻影のごとくそれぞれに映画館を退散していく。
*
「今は女の時代なんだよ」と1980年代当時、清水さんはそう言っていた。男たちは挫折を経験していて、未だに元気がない。男を物語の主人公に描くことが非常に難しいんだよ、という意味のことも言っていた。
彼はその後、木冬社での12月の紀伊國屋ホールでの公演「ラブレター」の出演を最後に木冬社を去った。時間をかけて、長い手紙を清水さん宛に書いてポストに入れた。後から人づてに「いい手紙だったよ」と清水さんが言っていたと聞かされた。彼はその頃から精神をいくぶん病んでおり、西新宿の十二社裏のアパートに閉じこもり、病院にも行かず、さらに悪化するままに彼の暗黒時代へと突入していくのであった。
*
そうやって、わたしが演劇界と関わったのはほんの2年弱の期間に過ぎない。そんなぺらっぺらの輩が偉そうに清水さんのことを書くんじゃないよ、という言葉もどこからか聞こえてくる。わたし自身、この文章を書いていて、途中で何度も止めようと思った。だが、やはり個人的に整理しておきたかった。加えて、この今の、インターネットで様々な情報が手に入るはずの時代にもかかわらず、清水さんに関する情報が本当に少ないと感じた。現在入手できる本の数も非常に少ない。直接関わった人間、間接的にでも影響を受けた人は数限りないほどいるはずだ。清水さんは偉大な劇作家だった。今、手元にある戯曲集をパラパラめくっただけでも、危険なことにすぐさま登場人物たちが立ち昇ってくる。短い期間であったにせよ、偉大な劇作家と直接関わって学んだ数多くの者たちのうちの一人として、わずかながらでも、そのある一面をどうしてもここに記しておきたかった。