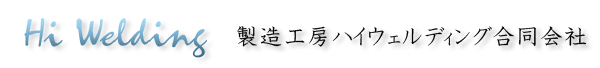追悼 清水邦夫 2 (清水さんへの二通目の手紙)
清水さんへ
大変ご無沙汰しております。
清水さん、ぼくのこと、おぼえていらっしゃいますか?
もし、忘れていたのなら思い出してみてください。
あれは確か、舞台「ラブレター」の稽古が始まる頃のことです。清水さんがラジオから流れてきたその曲を聴き、急遽録音したは良いが、曲名がわからない。この曲をぜひともこの舞台に使いたい。音響スタッフや詳しそうな知り合いに端から声をかけてみたが誰も知らない。困っている。
ぼくはその頃、稽古をサボって家にいました。稽古に出ていた同期の仲間が、以前にぼくの部屋でその曲を聴いたことがあることを思い出し、急いでぼくを呼びに来ました。実際に聴いてみないとわからないよ。どんな曲だろう。それでしぶしぶ自転車で西新宿の十二社から水道道路の一本道を通って代田橋の稽古場に向かったのでした。稽古場に入った途端、一同の視線を一斉に浴び、ぼくはサボっていた後ろめたさもあって、後退りするほどでした。
「いいからいいから」誰かに腕を引っ張られるようにして、その場に連れて行かれたような記憶があります。
珍しく興奮しているように見える清水さんがキューを出し、ラジカセからその曲が流れてきました。今でもあの曲を聞くと、あの時、あの場所に連れ戻されるような気がします。ぼくは応えました。
「スティービー・ニックスのカインド・オブ・ウーマンです。フリートウッド・マックのヴォーカリストでファースト・ソロアルバムである、麗しのベラ・ドンナの二曲目に入っています」
「持っているのか、レコードを」
「はい」
「うん、イワシタは木冬社にとって貴重な存在だ!」
思い出していただけたでしょうか?あの時のイワシタです。
まだ清水さんにお会いする前、初めて清水さんの戯曲に触れた時、この作者は「狂人」なのではないかと疑いました。脈略を超えた挑発的な言葉、まるで多重人格者かのような豹変ぶり、その人物だけが持つ特定の愛おしいこだわり、女々しさを隠さずに却って開き直るばかりか暴れだす男たち、降って湧いた危機を笑ってしまうほどの絶妙さでかわし、あるいは隠れ、逃げる。かと思えば、直情的な深刻さで軽薄さを朗々と語る人物達。ぼくが清水さんの戯曲に惚れたのは、それら台詞のテンポ、リズム、流れ、間合い、その感覚がぼくが持っていて、尚且、欠けていた窪みのような部分にフィットしたからではないかと思っています。
実際にお会いしてみて、一見、シャイで口数少なく、穏やかな人のように思えても、「この人は相当強靭な精神力を内に秘めているのだな」と感じました。そんじょそこらの反骨とは次元の違う、言ってみれば狂人との境、そのギリギリのラインまでにじり寄っていく。そういった境地から紡ぎ出されてくる言葉。二十歳そこそこの若造であったぼくは無知で頭は使いものにならない。ただただ、若さゆえの身体能力と神経感覚で戯曲の立ち上げに挑むしかありませんでした。
短い間ではありましたが、木冬社に在籍中、松本さんによるスタニスラフスキー・システムをベースとした数々のレッスンにより、身体能力と神経感覚の予備能力もかなり鍛えられたと思っています。
また、自分にフィットするものをとことん井戸の底まで深く掘り下げていくと、通底して他の未知のものに繋がっていて、そこを辿っていくと新たな知見を得ることができるということも実感しました。そのヒントを与えてくれたのが清水さん、蜷川さんです。そうやってぼくはアレン・ギンズバーグ、ジャック・ケルアック、ウィリアム・バロウズ、ジャン・ジュネ、アンリ・ミショー、ルイ=フェルディナン・セリーヌ、J・G・バラード、ギリシャ悲劇、ホメーロス、アンドレイ・タルコフスキー、アレハンドロ・ホドロフスキー、埴谷雄高、筒井康隆、中上健次等の作家達の作品群に出会い、それらは今でもぼくの感性のベースのベースになっています。そして、これらを経てからもう一度清水さんの戯曲に戻ってみると、これがまたやっぱり面白い。清水戯曲の超一級品ぶりに驚かされます。ただし、今だからこそ、そうやって接することができますが、当時の無知の若者にとっては非常に危険な書物であったとも思えます。
例えば、役者もどきとして安易に深入りしてしまうと、出口が見つからないほどに混乱します。その作用は、人格崩壊すれすれ、深層、潜在意識におとなしく静かに眠っていたものをブルブルと揺さぶられ、動かされ、目覚めさせられ、表層に呼び寄せられ、浮かび、終いにはわけもわからずに飛び上がってしまうという、いわばドラッグに似た作用をもたらす性質のものでもあったからです。個人的には強引に「清水戯曲病(笑)」とでも名付けたいくらいのものです。「妄想癖」も清水戯曲病の後遺症のひとつとしてもたらされます。強靭な精神力と、鍛え抜かれた制御力、松本さんに代表されるそうした役者としての経験を積み重ねたプロフェッショナルで高度な技術だけが「清水戯曲病」にかからずに済み、本来の戯曲と対等に渡り合える方法なのではないでしょうか。
ぼくはもともと役者志望ではなかったことと、病の前兆のようなものを感じて、早めに木冬社を去りました。それは一通目の手紙に書いたとおりです。今はどうにかこうにか製造業の現場に身を置き、ヒーヒー言って、バタバタとのたうち回りながらもなんとか元気でやっております。これは他の人にはわからないと思いますが、ぼくのなかでは演劇に関わったことと、今の、ものづくりの現場は、緩やかで、それでいて良く撓る確かな一本の線で繋がっているのです。
舞台「ラブレター」では、ぼくへの当て書きで、吉行和子さん演じる「さやか」の病院のお友達のうちの一人である「久米さん」の役を与えてくださいました。その久米さんの台詞「角をきちんと、角を・・・」はぼくの持つ本質のひとつでもあり、これは製造業にとってはとても大事なことで、時々つぶやきそうになり、変に役立っています(笑)。
清水さんの生涯の中でも、あるひとつのピークであった時代の代表作「タンゴ、冬の終わりに」の初演に関われたことは、ぼくの数少ない財産のうちのひとつです。無知の若者だったぼくは偉大な先人である清水さん、松本さん、蜷川さん、平さん達から数々のヒントを得、学び、探り、種を得たことで、その後のぼくの骨格を形成することができたのだと思っています。ここに最大限の感謝を記したいと思います。お世話になり、本当にありがとうございました。
どうぞ安らかにお眠り下さい。