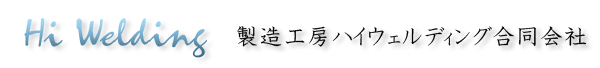追悼 遠藤勝美 1
一人の溶接工として、わたしが個人的に最も影響を受け、敬愛する先達の溶接工・遠藤勝美氏が癌でこの世を去ってから早二年が過ぎ、もうすぐ三年になろうとしている。
2020年11月7日永眠 享年75歳。
コロナ禍であったために、この間、面と向かってのお別れの挨拶もできずに、何かが引っ掛かったような、区切ることができない時間を過ごしてきたのだが、今年のお盆の期間中に奥様のご実家にてようやく御佛前にお線香を上げることが叶ったのだった。
過去、この「溶接雑記」にも何度も登場してもらっている「師匠のEさん」とは遠藤勝美氏のことである。今回実名で登場してもらうのは、インターネット上に、この稀代の名工である職人「遠藤勝美」の名前を、そしてその功績を永遠に、強く刻んでおきたいと思ったからだ。
遠藤さんは、厚生労働大臣に表彰される「現代の名工の方々」のような「育ち、お行儀の良さ」は持ち合わせていなかったが、その「総合的な溶接技術」はわたしの知る限り、間違いなくナンバーワンの存在であり、何よりも先駆者であった。それは失敗を含めた様々で数々の経験から得た独学独自の理屈で裏付けされており、初めて持ち込まれた難しい仕事や、よそでは「できない、無理だ」断られた仕事も、なんなく引き受けてきたのだった。
「オレはよぅ、言葉じゃうまく説明できねぇけど、理屈は解るんだよぅ」
これは遠藤さんの口癖で、遠藤さんの仕事とはその「言葉にならない理屈」を身体、手先を使って「証明」、少し大仰に言うならば「表現」してみせてきた、とも言える。
人の生涯というものは、この世に生を受けたタイミングと環境、そして、その人の生き抜いた時代背景との巡り合せにどうしようもなく左右されるものだと思う。わたしがこの金属加工業界に足を踏み入れた時(1990年代)は、既に日本の製造業の内実は業種によって枝分かれ、細分化されていた。大掛かりな設備が必要な造船やプラント、ロボットを導入した板金やプレス加工が多く大量生産が必要な車や家電、それらに連なる大量多種の部品類、大量消費される食品類、その食品業界などで必要とされる主にステンレス製の自動化ラインの機器類、そして1980年代に世界シェアトップを走り続けていた半導体業界など、それらは各々に棲み分けられ、上流から下流までおよそその分野専門としてのサプライチェーンが構築されていた。
同様の品種の製造であれば、設備面において材料や機械、金型や冶具の工夫といったものが使い回せ、コスト、効率において有利に展開でき、また、専門性に強みがあるので、特化した技術力も自ずと上がってゆく。その反面で業種の異なる分野の製品は、規定されたルール、求められる品質、あるいはどういう使い方をされるのかといった具体的なことに慣れないために、手を出しにくくなる。
わたしが溶接工として、たまたま運良く入社した中小規模の会社の溶接の現場は、ほぼ9割以上が半導体製造装置のチャンバーや、装置に付随する配管類で占められていた。溶接法はすべてTIG溶接で行い、溶接後のパーツを社内の組立部門が他のパーツや、電気部材、配線も含めて、電源を投入すればほぼ稼働する完成品として組み上げ、出荷し、メーカーに納品していた。そこでの溶接の現場は「溶接の品質に特化して、溶接だけしていればよい」というスタイルで、同様の品種のものを来る日も来る日も溶接していた。それはそれで目が肥え、特に半導体製造装置の類はクリーンルームを必要とし、部材を洗浄後もチリ、ホコリ、傷、不純物、油脂成分などを嫌う上に、溶接の溶け込み具合はもちろん、溶接後の焼け取りを含めた見た目の品質基準が非常に高く、厳しく、耐真空が前提で繊細で精密な溶接が求められ、仕事として相当鍛えられた。また、初期の教育面においても「日電アネルバの坂本教室」の流れを汲んでおり、指定された各種類のテストピースを日電アネルバ社に提出し、厳しい品質検査の上でそのすべてが合格しなければ、実際の製品の溶接作業に従事できないという決まりがあったことで、悪い癖が付く前に、つまりほぼ白紙のまっさらな状態から技能技術の基礎、基本を学ぶことができたことは、非常に恵まれ、幸運だったと思う。なお、「日電アネルバの坂本教室」の坂本氏も日本の耐真空精密溶接の先駆者であることをここに付け加えておきたい。当時は、「坂本教室に合格した基準」が業界のスタンダードであり、他の半導体製造装置メーカーにとっても「この基準をクリアしているのであれば、この会社に外注してもよい」という判断材料になっていたのである。そういう意味でわたしは幸運にも、そこまではまあまあ「育ちが良かった」と言えるだろう。
ただ、毎日同じ様な仕事をし続けていると、飽きもくるし、不安がつきまとうようにもなる。仕事上ではそれなりに評価されてはいたものの「このままでは井の中の蛙、溶接以外はまるっきし役に立たない溶接バカ、もっと他の知らない世界とも向き合いたい」と窮屈さを感じていた時に出会ったのが遠藤さんだった。正確には「出会った」というよりも「見つけた」と言う方がしっくりくる。
ある時、当時勤めていた会社での受注量が限度を越えたために、外注企業に協力してもらわないとならない事態になり、営業担当者が、急いで外注企業を探しに回った。とはいっても、限られてしまうのだった。なぜなら「坂本基準」があるからだ。どこも、手一杯、あるいは手に負えない難物らしく、お手上げ状態の中で探し出してきたのが、当時昭島市にあったF精工という会社だった。ただし、営業担当者は頭を掻きながらその会社の説明を始めた。どうやら、その会社の技術レベルは相当高いらしいのだが、東京多摩地区の製造業の間では「暴れん坊」の異名があり、大手半導体製造装置メーカーと大喧嘩をして、そのメーカーに対して「今後一切関わらない」と啖呵を切ったのだということだった。メーカーの設計者に直接設計変更や文句を言い放ち(実は、ここの部分はこういうふうな嵌合、形状で組み合わせたほうが、気密、真空に適しているといった具体的なアドバイス)、そういう関係になってしまったということだった。
何を隠そう、外注として協力して欲しかったのは、そのメーカーそのものの製品であり、「F精工」という会社名は営業担当者が「難易度が高いので外注先がなかなか見つからないんですよ、どこだったらできますかねえ」と、メーカーに相談を持ち込み、そのメーカーの担当者から聞いたのだという。他にももっと些細な、ごちゃごちゃとした事案もあったようだが、詳しくは知るすべもない。何はともあれ、わたしが勤めていた会社がそのメーカーから受注し、F精工に協力してもらい、こちらの会社として納品すれば問題はないとのことだった。F精工としても啖呵を切ったものの、得意としている技術を途切れさせたくないのと、こちらの会社、営業担当者がクッションとなってくれる分、直接の負担が軽くなると考えたのかも知れない。
そうしてF精工から納品された、初めての製品である「真空チャンバー」を目にした時の衝撃は今でも忘れられない。機械加工、溶接、仕上がり具合とその何もかもの品質レベルが数段上をいっている製品として、わたしの目に飛び込んできたのだった。一言でいえば、「製品として輝いていた」のだった。例えば機械加工における表面の目の細かさ、粗さの程度。目の細かさは必要最低限で良い。真空を保つためのシール面は厳密に必要なだけ細かく、しかしその他は図面に指定された公差内の粗さで良い。装置内でボルト接続で組み立てるための取っ手の表面部分などは、必要以上に細かくしてしまうと傷がつきやすく、かえって目立ってしまい、逆効果になってしまう。要は緩急を自在に使い分けており、その判断力の的確さに感心したのだった。また、溶接は棒を入れてガッチリ、しっかりと肉盛り溶接されており、ナメ付け(溶接棒を使わずに金属部材同士のみを溶かし合わせる溶接方法)箇所はほぼない。真空に関わる場所ではないのだが、溶接箇所が狭いために、溶接トーチの先端部ノズルが入らず、溶接できなかった部分(メーカーにその箇所は溶接しなくとも良いと許可をもらっていた)も肉盛り溶接で全周溶接されてあった。溶接焼け取り方法も電動ブラシで磨くのではなく、電解式で仕上がっていた。他にも細かく言えば切りがない程の違い、差があった。「今まで知るすべもなかった」「思いもつかなかったアプローチの方法」そして「決定的な敗北感」などが、それまでのわたしに欠落していて、しかし、待ちわびていた凹みのような部分に「ストンッ」と嵌ったのだった。先に述べた「見つけた」という言葉はこの時の感覚そのものであり、この納品された「真空チャンバー」のなかにわたしは「遠藤さんを見つけた」のである。