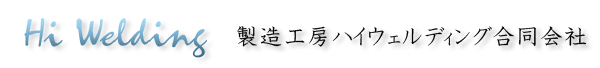追悼 遠藤勝美 2
実際にF精工に足を運び、現場の職人達と対面してきた営業担当者に、わたしはこの溶接を担当している人物の印象を聞いてみた。
「けっこうなオッサンだよ、老眼鏡かけていたからね。それも近眼用の眼鏡の上に被せるようにしてさ、眼鏡を二重にかけていたんだよ、変わってるよね」
「うちにもある電動の回転ポジショナーがあったんだけどさ、それ使ってないんだって。なんだか回転の調整がどうとかこうとかで、それで自作の手回しのロクロみたいな物で回しているんだってさ」
「電解式の焼け取り機は買うと高いからって、そのオッサンが自分で作ったらしいよ。電解液だけは買っているみたいだけど」
それらを聞いて、わたしはそのオッサンに会うしかないと思った。できることなら、一緒に仕事を、つまり弟子入りしたいと思ったのだった。また、そのオッサンだけでなく、F精工のチームワークに未知の魅力を感じた。F精工から納品に来る担当者は、わたしと同世代の旋盤工でありながら、自ら営業もこなすという、なにか別の次元の才能にも満ち溢れているAさんで、納品に来ると、必ず溶接の現場にも顔を出してくれるようになった。わたしがF精工が納品する製品を称賛しているのを知っているからだった。
「営業っていっても、うちはほら、製品を納めれば、それが営業だから。イワさん(わたしのこと)のように見る人が見ればわかるでしょ」
「うちは現場主義、職人集団、現場の発言力には誰も敵わないよ」
「イワさん、うち来る?イワさんだったら、いつでもウェルカムよ」
Aさんとお互いに「からかい」とも取れる軽口を叩ける間柄になってくると、わたしは次第に自分が担当している仕事の引き継ぎのことを真剣に考え始めるようになった。そして、それから約半年の間程、同じ現場の年若い後輩の溶接工に教え伝えることで、それまでお世話になったこの会社での最後の役割を果たせたと、許しを求めるように会社に辞表を提出したのだった。ルールに反する気がして、事前にF精工にもAさんにもいっさい話はしなかった。直接F精工に連絡を取ったのは最後の仕事を終え、正式に退社ということで、私物を含めて何もかも引き払った翌日のことだった。その日の記憶は、風景として今でも鮮明に憶えている。東八道路沿いにあるファミレス、デニーズの店内から、わたしは初めてF精工に電話をかけたのだった。Aさんに代わってもらい、そこでおおまかな事情を話し、その足で地図を確認しながら車でF精工に向かったのだった。
昭島市にあったF精工は川沿いの道に突き当たるT字路の角にあり、かなり広い敷地を有していた。本棟の一階が主力の機械加工の工場で、二階には事務所、更衣室、食堂などがあった。その他にも中庭、駐車場を経て、別棟として二階建ての板金工場があった。どれも戦後からの古い昭和感漂う、いわゆる町工場といった建物で、中庭には使われなくなった古い機械や定盤などが積まれ、ブルーシートに覆われて野ざらしにされてあった。連絡すると駐車場まで出迎えに来てくれたAさんに先導されて、道路に面した本棟の一階の扉を開けると、すぐ左手に二階へと向かう階段があり、扉の先のもう一つの別の扉を開くと、そこが溶接場となっていた。二重眼鏡をかけたあのオッサンこと遠藤さんとはじめて対面したのはこの時だったのだが、何故かはじめて会ったという気がしなかった。遠藤さんの方でも、Aさん経由でわたしの存在を以前から聞いていたらしく「ああ、おめえかぁ」という感じで接してくれたのだった。おそらく「取引先に、遠ちゃん(Aさん達にはこう呼ばれていた)のことを褒めるやけに変な溶接工がいるんだよ」とでも聞いていたのだろうと思う。
「あとでまた寄りなよぅ」
溶接場のもう一人の年若い溶接工Cさんも、忙しそうななかでそれまでの手を止め、親しげに挨拶してくれた。Aさんに一通り工場内を案内される。行き交う職人たちと都度、挨拶を交わす。現場には活気があり、ベテランから年若い職人まで年齢層も幅広く、仕掛品である製品群を見ても多種多様な間口が開かれているという空気を感じた。壁で仕切られた部屋には、最近導入したばかりだという大型の超音波洗浄機があり、その横で梱包、出荷の準備をしている遠藤さんと同じ位の年格好の人物をAさんに紹介され、挨拶する。
「うちの親分、Kです。で、専務なんだけど、仕事ばっか。営業の最前線で毎日闘っています」
「よく来たねぇ。Aから聞いてるよ。よしっ、さっ、じゃあ、二階に」
自分の好奇心を何よりも最優先にして行動してしまっていることの自覚は多少なりともあった。それゆえに、F精工への転職がそう簡単に、スムーズにいくとは思っていなかったのだが、好々爺であるKさんからの提案もまた、想定外のことだった。
「うちに来てくれた気持ちは嬉しいんだ。ただ、誰も傷つけない、ということはとても難しいことでねえ。イワさんがいた会社とうちは今後も仕事上の取り引きが続くわけさ。引き抜かれた、引き抜いた、と思われてしまうような関係は良好じゃないと思うんだ。そこで、考えたんだけど、どうだろう、一年間、前の会社とは関係のないところで辛抱してくれないかな。何だったら、いくらでも紹介するから」
言われてみればもっともで、その通りだった。それまで、そういった気配りに気が回らない自分の愚かさを恥じ「調子こいてんじゃねーよ!」という怒鳴り声がどこからか聞こえた気がした。その時は「少し考えてから、ご連絡いたします」と答えるのが精一杯だった。
まあ、それはそれとして、気持ちを切り替え、せっかくだからと帰り際に遠藤さんのところに寄った。どうしても聞いておきたいことがあったからだった。
「あの狭いところに届くノズルはどんなのを使っているんですか?」
遠藤さんが使うメインの作業台はC形鋼で頑丈に作ったフレームの上に、見るからに使い込まれた、それでいて錆一つないサブロク(1820mm×920mm)の定盤が乗せてあり、作業はその上で行い、定盤の下のスペースには様々な道具が詰まった箱や冶具で占められていた。定盤の右側にあたる窓際の壁には引き出し満載の道具棚があり、パッと、そのうちの一つを引き出すと、そのノズルを取り出して「これよぅ」と、見せてくれたのだった。パナソニック社製のTIG溶接用ノズルNo.5(セラミック製)の先に8mmのステンレス製パイプを差し込んで先端を必要なだけ伸ばしてあった。それは思ってもみなかったアプローチだった。アークを発する電極であるタングステンとパイプとの隙間が恐いほどに狭くなりそうだったからだ。
「ステンのパイプって、これじゃ、アークがこっちのパイプの方に飛んじゃわないですか?」
「(ああ、おめぇ、いいところに気づくなぁ。話がはええや)だからよぅ、クレータなしで強めの電流で最初に飛ばすのよぅ。一度、向こうに飛んじまえば、後はこっちのもんだからな。それとタングステンは2.4じゃなくてテンロク(1.6mm)でな」
それを聞いて、わたしは「凄え!」としか返せなかった。2023年の現在では海外のメーカーから様々な種類、気の利いた形状のセラミック製TIG用細ノズルやガスレンズといった名称のシールド性に優れたノズルが販売されている。そしてそういったノウハウも、今ならネットから容易に情報が取れるが、90年代当時としては画期的な発想だった。
次にわたしは道具棚と奥のCさんの作業台である定盤の間に、押し込むように収まっている回転ポジショナーを指して聞いた。
「これ、使っていないって本当ですか?」
その途端に遠藤さんは笑い出した。あぁ、あの営業マンに言ったことか?
「あれは、からかっただけよぅ。モノを知らなそうだったからよぅ」
その後、遠藤さんと長く付き合うなかで、こういった人をからかったり、おちょくったりする少し意地悪な癖があるのを時々見ることになるのだが、それはその相手がどれほど知っているのか、どこまで知りたいのか、本当にそのことに興味があるのか、といったことを判断する材料として、相手を試していたのではないかという気がしている。もちろん、からかわれた方は気分が悪いだろう。ただ、からかわれたこと自体に気付かないままでいることも多い。だが「本気」で質問すると、「本気」で遠藤さんなりの理屈で正直に応えてくれる人なのだった。
「バリバリ使っているよぅ。これ使わなきゃ、仕事になんねえだろぅ」
当時、半導体は微細化とともに、シリコンウェーハのサイズがそれまでの主流だった200mm(直径)から300mmへと移行する時期で、それに合わせて製造装置も大型化されていったため、手掛ける真空チャンバー(円筒形状)や、水冷フランジ(円盤形状)などの直径が450mm、大きいものだと600mm近くにもなった。水冷フランジは、効率よく冷却水を循環させる環状の溝に蓋をすることで一体化させる形状のものが多い。溶接工程ではその蓋の外周と内周を全周溶接する。仮付け後に、回転ポジショナーのテーブルに設置して電動で回転させて溶接するのだが、直径が大きくなるほど回転スピードを下げなければならない。それだけに一周する時間は長くなる。その間、溶接姿勢はほぼ固定でなので、時々眠くなるほどだ。
「ナメ(付け)でやっているんだって?よく割れねえなぁ、歪み取りはどうしてる?」
「手動の油圧シリンダーで押してます、10トンかな。遠藤さんのやり方、肉盛りで溶接してあって驚きました。だって、開先とって棒入れているから電流高めでしょう、歪みが凄いんじゃないかって、歪み取り大変でしょう?」
「うちは板金工場に昔ながらの縦型の大型プレス機があるからな、100トン。それでガッシャンよぅ。ま、それだけじゃないけどな。そいで、歪みしろはどんくらい取ってんの?」
「2から3mmってとこですかね」
「うちは1mmよぅ」
「!!!」
言葉にならなかった。どういうことかというと、溶接は歪み取りとの闘いでもある。アーク熱で溶かされている間、金属は膨張している。それが、溶接後、大気中で冷えていく間に驚くほど収縮する。高い電流を使うほど、歪みが大きくなる。なるべく歪みを抑えるためには低い電流でスピードも早めに仕上げるのが良いのだが、当然ながら溶け込みは弱くなる。一方、溶け込みを優先して、開先を取り、棒を入れてしっかりと肉盛り溶接した場合は入熱量が多いために、歪みが大きくなる。こういった水冷フランジ(肉厚20mm以上)のような場合、溶接前にあらかじめ「歪みしろ」といって、フランジには仕上がり寸法よりも何mmか余分に肉厚が加えられてある。溶接後に歪み取りをしてから、もう一度機械加工(この場合は旋盤)でOリング溝を仕上げたり、「歪みしろ」分を削り出すことで平滑さを出して完成させる。「歪みしろ」が1mmということは、溶接後の歪み取り作業での平面度を1mm以内に抑えなければならないということを意味する。そこまで圧力をかけるということは、ナメ付け程度の溶接では割れてしまうことだろう。物にもよるのだが、こういった肉厚が20mm以上あるフランジ物はガッチリ溶接して、ガッチリ歪み取りをするというのが遠藤さんの方法論であり、理屈だった。それが正しいかどうかは断面を想像してみれば明らかだった。「歪みしろ」が2から3mmということはそれを削り、底面だけの平滑さ(図面上では問題ない)を出せたとしても、断面で見れば肉厚にそれだけバラツキが生じているということになる。
その後も、何かと話しているうちに「おめぇにはオレがやろうとしていることがわかるようだな」とでも思ってくれたのか、自作の「電解式の焼け取り機」を自慢気に見せてもらったり、導入したばかりの「大型超音波洗浄機」を実際に稼働させて見せてくれるのだった。
「これを導入する前は何で洗浄していたんですか?」
「ママレモンよぅ」
「またぁ、からかってんですか?」
「本当だよぅ、小さい洗浄機はあったんだが、こう大きくなってくると入らねぇだろ。いろいろ試したんだが、ステンを洗うにはママレモンが一番いいんだよぅ」
面白い人だと思った。こういう自在な振れ幅、とりあえずは手に入る物で工夫する、それでもなかったら自分で作ってしまう。「ちょっと貸してみな」と、遠藤さんがわたしの金属フレームの丸形眼鏡を指すので、わたしは眼鏡を外し、遠藤さんに手渡した。「きれいになるんだぜぇ」といって、眼鏡をステンレス製の網籠に入れると稼働ボタンを押した。真夏の蝉の声を薄めたような、独特の超音波の音が耳に響く。微細な気泡が水面に立ち昇ってくる。ほんの数十秒、一分も経たないうちに、様子見のように網籠を引き上げた途端に遠藤さんが声を上げた。
「あれっ、おいっ、こりゃまぁ!」
網籠を覗くと眼鏡のレンズが白く曇っている。遠藤さんはとっさに考えている顔をしている。条件反射のようにその原因と理屈を考えていたのだと思う。考えながらベンコットでレンズを何度も拭いてみている。
「・・・!、コーティングか。オレの眼鏡はコーティングなしだったからセーフだったのかぁ。ごめんよ。悪いなぁ」
「いや、いいんですよ。眼鏡はもう一つ持っているから。車のなかにあるんですよ」
夜間の運転用に度を一段階あげた眼鏡がダッシュボードのなかにあるはずだったので、そう焦りはしなかった。
「本当にごめんよ。ちょと考えさせてくれなぁ。修整するからよぅ」バツが悪そうに遠藤さんが心底謝ってくる。
「大丈夫ですよ。これでまた知見が増えたじゃないですか。レンズに施されているコーティングは、産業用の強い超音波には弱いんだって」
「遠ちゃん、やっちゃった~?」
背後から様子を見ていたのだろう、Aさんが茶化すように声をかけてくる。わたしは遠藤さんの手から眼鏡を受け取り、いつもの通り耳にかけた。曇っているレンズの向こうに一生懸命に笑いをこらえている遠藤さんの顔がうっすらと見えた。わたしはそのまま後ろを振り返り、Aさんのいるであろう方向に向かって指でO.K.のサインを送った途端、爆笑の嵐を浴びることになった。白く曇っていてよく見えないのだが、いつの間にかAさん以外にも何人かの職人たちが集まっているようだった。
その時、わたしはそれまでの人生で感じたことのない満足感のようなものを得ていた。そして感謝したかった。笑われてはいるが、その笑いのなかに「仲間として受け入れる準備はできているよ」というような温かいメッセージを感じたからだった。眼鏡はもう3年以上も使いまわしている物だし、お金を出せば買うことができる。だが、こういう仲間達、特にその後師匠となる遠藤さんとの出会いはお金で買うことができない。
この日、遠藤さんはわたしの具体的な質問に何も隠すことなく応え、正直に、手の内を見せてくれた。そのお礼を、深く頭をさげて遠藤さんに伝えた。
「待っているからよぅ」
そう、最後にかけてくれた言葉にどれほど励まされたことだろうか。さあ、一旦、頭を切り替えよう、とわたしはその日のF精工を後にしたのだった。
機会があればそのうち続きも・・・。